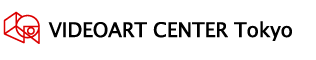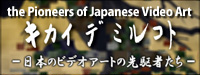Move on Asia/Crash&Networkシンポジウムから
Move on Asia/Crash&Networkシンポジウムから
 シンポジウムの会場となった延世大学
シンポジウムの会場となった延世大学
2006年3月17日からソウルのオルタナティヴ・アートスペース LOOP にて、アジアのビデオアートに焦点を当てた展覧会「 Move on Asia 2006 」が開催された。これは2004年にLOOPの呼びかけに応じて、アジアのアートグループやスペースがビデオ作品を持ち寄った巡回展「Move on Asia」に端を発しており、二回目となる今回は展覧会に併せて 「Crash and Network」 というテーマでのパネルディスカッションとシンポジウムがソウルの延世大学にて催された。延世大学の教授がホストとなり、パネリストに LEEDS 大学教授ヴァナリン・グリーン、南イリノイ大学教授ジョツナ・カプール、オーストラリア映像センター(ACMI/南メルボルン)からマイク・スタッブス、アジア・アート・アーカイヴ(AAA)の韓国担当の調査員アイリス・ムーン、オルタナティヴなネットワーク作りをしているアートグループの代表として、インドネシアの「ルアンルパ」のアデ・ダルマワン、そして VCT/ ビデオアートセンター東京からは筆者が招聘された。